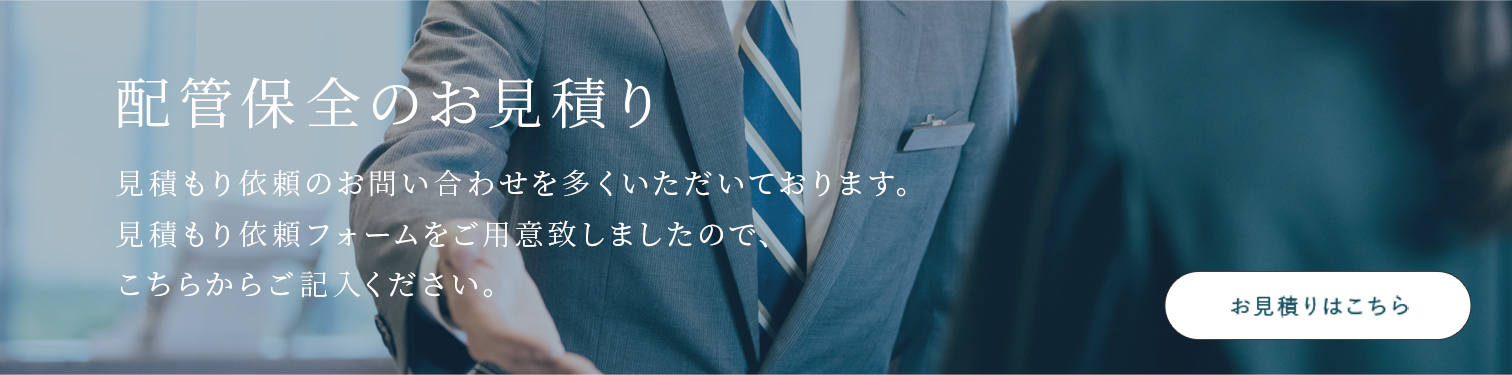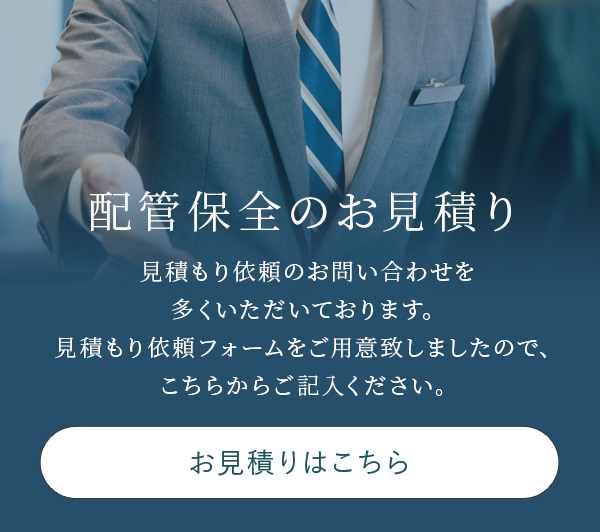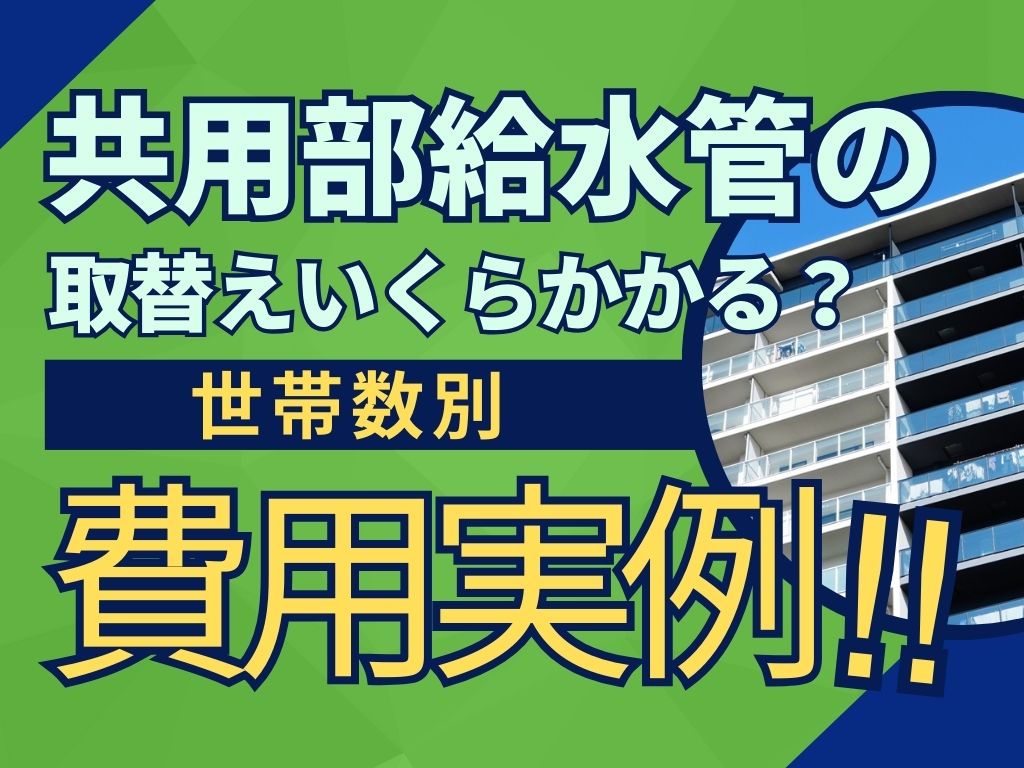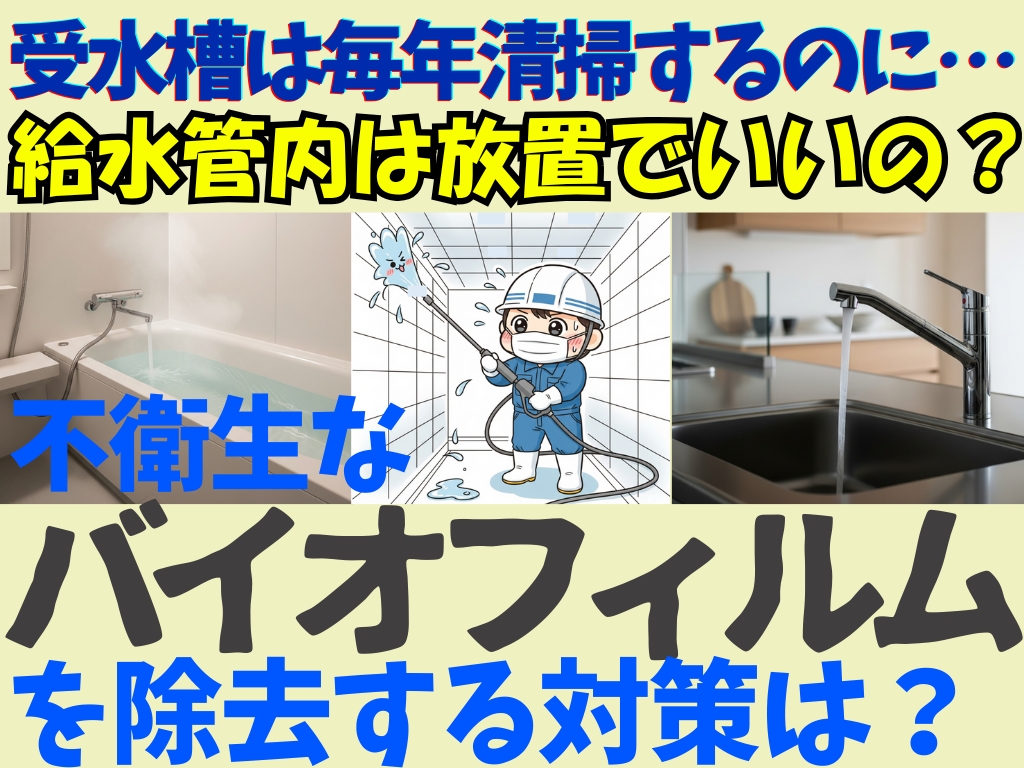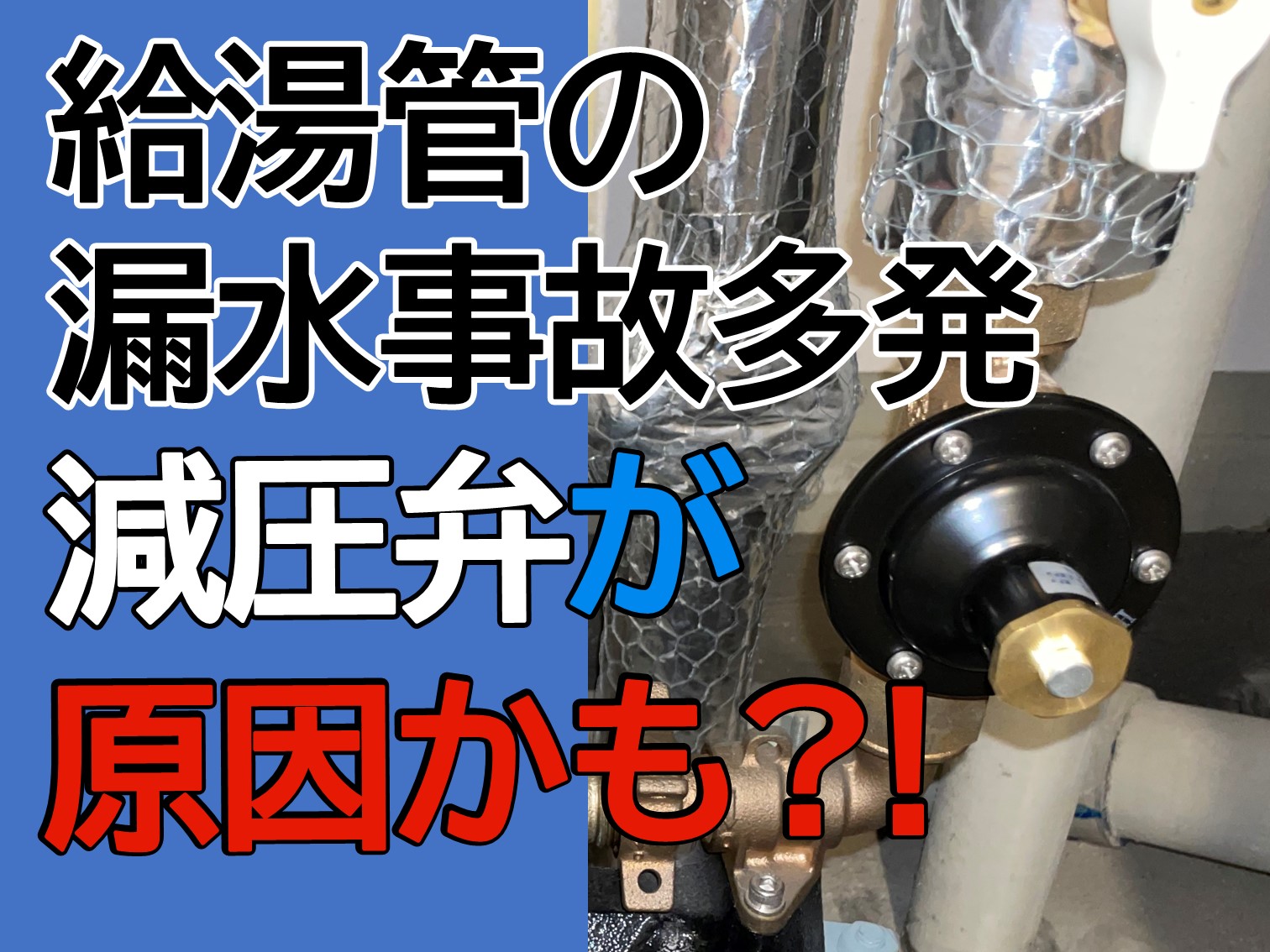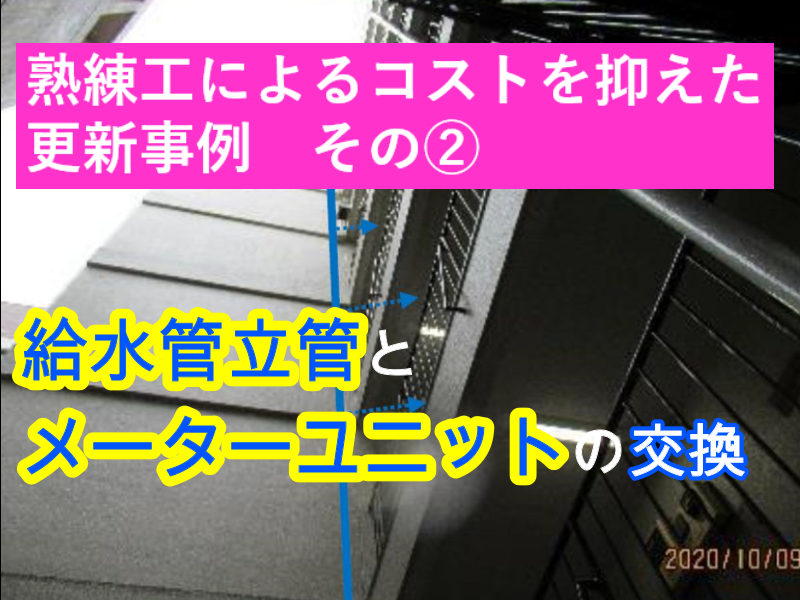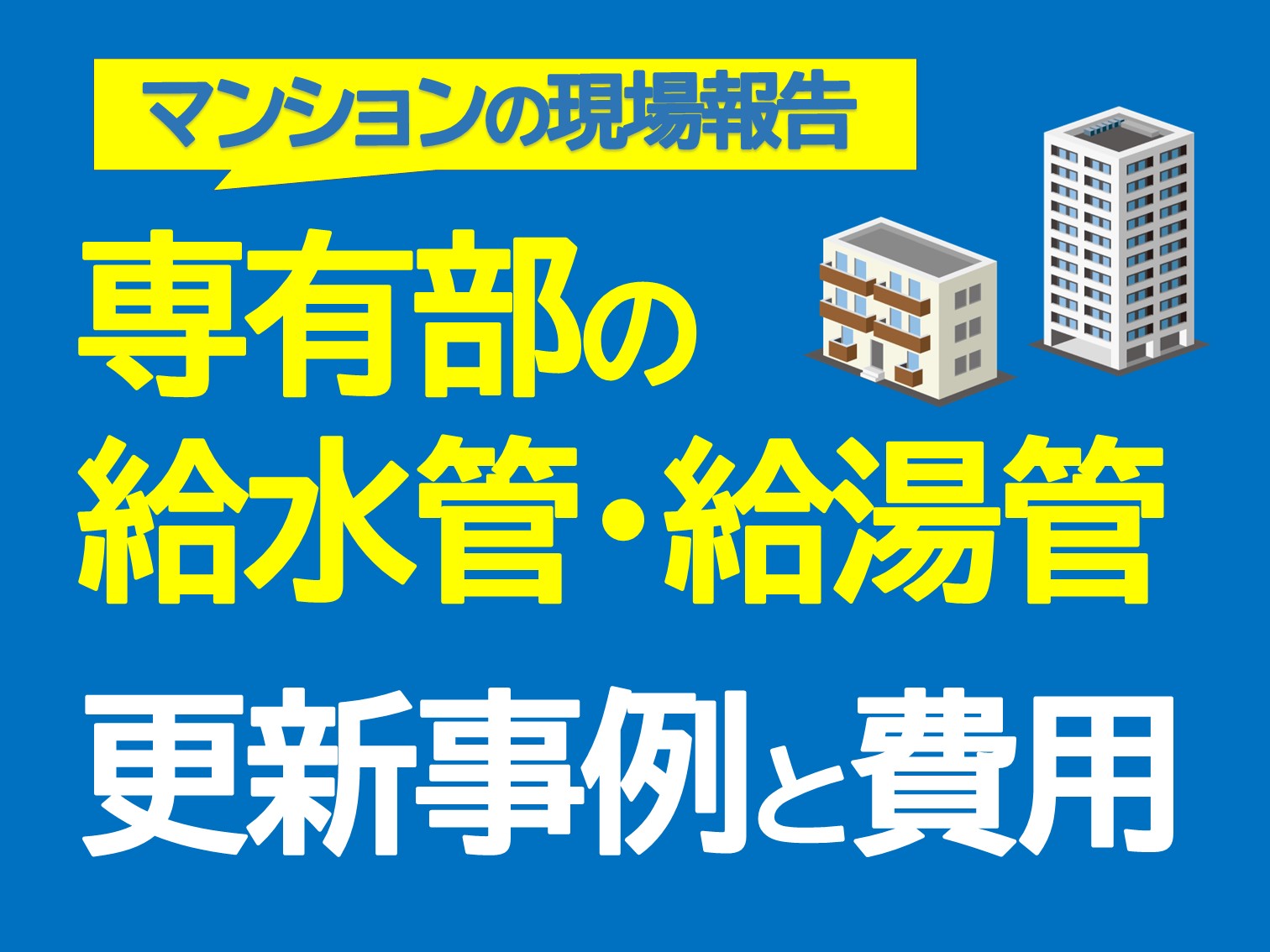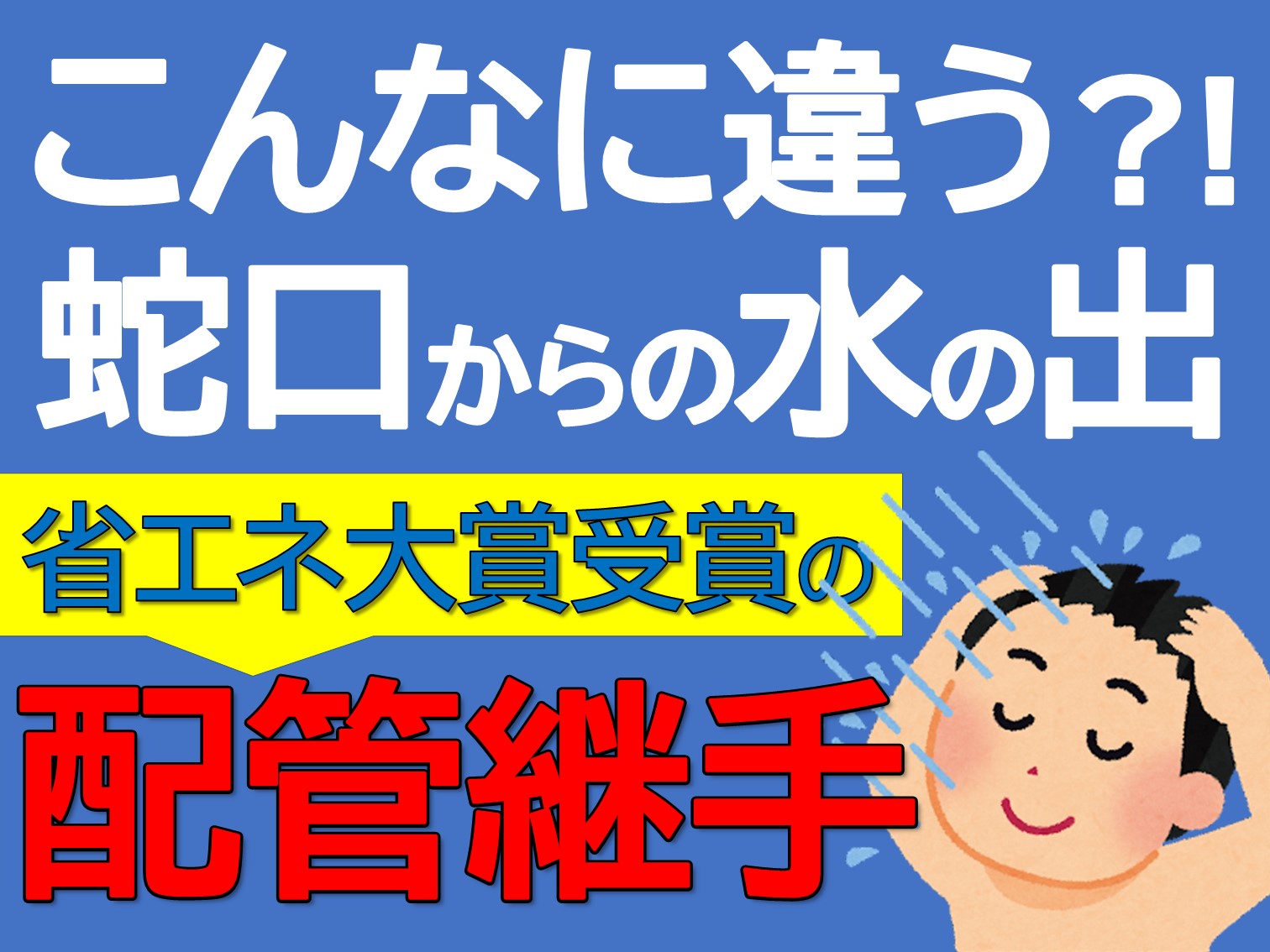勉強部屋
【実例公開】200世帯マンション給水管更新 世帯負担40万円→20万円!半額で工事できた理由
2025年10月1日
この記事のカテゴリー : 給水・給湯管の保全

動画
工事概要の説明
まず、工事の概要からお話しします。 今回工事を行ったマンションは築35年以上で14階建て、厳密に言うと200世帯に近いマンションですが、わかりやすくするために200世帯に換算してご紹介します。 工事内容は、地下1階から各住戸までの給水管立管と各住戸の水道メーターまわりを全面更新します。 取替工事を行った理由としては、築35年経ち、給水管立管はライニング鋼管のため、そろそろ交換時期だったこと。 各住戸の水道メーターまわりは錆びやすい材質で築35年で漏水リスクがかなり高まっていたこと。 また、昨今の工事費の値上がりでいずれ取替えることを考慮すると、 今後の更なる値上がりの前に取り替えたほうが得策といった理由から工事を行うことになりました。 配管の材質は、地下1階から各住戸の水道メーター廻りまでは、エスロンハイパーという耐震性にも優れ、漏水事故のリスクの少ない樹脂管を使用しました。 受水槽から地下1階までは、すでにエスロンハイパーに替えられていたので、そこから上の各階の給水管立管の取替え工事となりました。 配管の素材としてはステンレス配管が挙げられることがありますが、ステンレス配管は継手部分のパッキンの寿命が短いことや、耐震性でも樹脂管のエスロンハイパーに劣ることから、ステンレス配管は採用しておりません。
各住戸では、水道メーターまわりを減圧弁付きのメーターユニットに交換しました。
メーターまわりの配管の材質は、ステンレスのソフレックスという材料を使用しました。
新規配管は露出配管ではなく、各住戸のパイプシャフト内に隠蔽して配管しました。
断水は各住戸で2回。工期は30日弱で無事、完了しました。
配管の素材としてはステンレス配管が挙げられることがありますが、ステンレス配管は継手部分のパッキンの寿命が短いことや、耐震性でも樹脂管のエスロンハイパーに劣ることから、ステンレス配管は採用しておりません。
各住戸では、水道メーターまわりを減圧弁付きのメーターユニットに交換しました。
メーターまわりの配管の材質は、ステンレスのソフレックスという材料を使用しました。
新規配管は露出配管ではなく、各住戸のパイプシャフト内に隠蔽して配管しました。
断水は各住戸で2回。工期は30日弱で無事、完了しました。
施工前後の状況
実際の施工前と施工後の様子をご覧ください。 工事後の画像で青い配管が共用部の立管で樹脂管のエスロンハイパー製です。
水道メーターまわりの1次側と2次側は保温材で巻かれた柔軟性のあるステンレス製のソフレックス配管です。
下の画像は、切断した既存配管です。銅とスズの合金の砲金と、直管部のライニング鋼管との接続部は、異種金属接触腐食により、右下の画像のように、かなり錆びコブが生成され閉塞寸前の状態でした。
また、左下の画像は直管部の配管ですが、築35年以上経過してヌメリが発生して薄茶色に変色しているのがわかります。
工事後の画像で青い配管が共用部の立管で樹脂管のエスロンハイパー製です。
水道メーターまわりの1次側と2次側は保温材で巻かれた柔軟性のあるステンレス製のソフレックス配管です。
下の画像は、切断した既存配管です。銅とスズの合金の砲金と、直管部のライニング鋼管との接続部は、異種金属接触腐食により、右下の画像のように、かなり錆びコブが生成され閉塞寸前の状態でした。
また、左下の画像は直管部の配管ですが、築35年以上経過してヌメリが発生して薄茶色に変色しているのがわかります。
 今までは、11階から14階までは減圧弁が付いてなかったのですが、将来の直結増圧化を見越して、14階まで全て減圧弁を設置しました。
工事直後は、一部の住戸から水圧が弱くなったというご意見があり、水圧を調整したところ、最終的には満足いただける水圧となりました。
今までは、11階から14階までは減圧弁が付いてなかったのですが、将来の直結増圧化を見越して、14階まで全て減圧弁を設置しました。
工事直後は、一部の住戸から水圧が弱くなったというご意見があり、水圧を調整したところ、最終的には満足いただける水圧となりました。
見積もり金額の差の分析
さて、本題の見積もり金額の差について詳しく見ていきましょう。 最も高い業者の見積もりは約8500万円、世帯あたりでは42万5千円。 配管保全センターが紹介して採用された業者は約4000万円、世帯あたりでは20万円。 実に倍以上の差がありました。なぜこれほどの差が生まれたのでしょうか。 差がついた4つの理由 さまざまな要因が考えられますが、ここではどのマンションでもあてはまりそうな4つの理由を挙げてみました。
1. 設計コンサルタントを入れない直接発注
一つ目は、給排水管の更新工事は総じて言えるのですが、工事自体は比較的単純なため、わざわざ設計コンサルタントを入れずに直接、業者に発注したということです。 設計コンサルタントを入れる場合、当然ですがその分の費用が発生します。 また、場合によっては設計コンサルタントと関係性を持つ業者のみしか見積もりに参加しない状況になる事が多く、競争が制限され、見積りに参加した業者の見積り額自体が相場よりも高くなる可能性もあります。 最近、マンションの改修工事の談合問題が話題となっていますが、そういったことが起きやすくなる傾向にあるということですね。 さらに、直接施行する業者までの間に、介在する会社や業者が多ければ多いほど中間マージンが発生します。 施工を管理する業者、設計コンサルタント、管理会社と絡めば、費用が何割も追加され、最終的には大幅にコストが上がってしまうことが多いです。 以前からお話していますが、給排水設備の工事は比較的単純な工事が多く、設計コンサルタントをいれない直接発注によってかなり費用を抑えられる場合が多いといえます。2. 組合主導による適正な業者選定
二つ目の理由として、管理組合が主体となって業者選定をしたということです。 理事会や修繕委員会が積極的に関わり、複数の業者から見積もりを取って内容を精査しました。 今回の工事では、設計コンサルを入れずに、配管保全センターが外部の専門のアドバイザーという立場になったんですが、配管保全センターからのアドバイスを管理組合が受けながら、最終的な判断は組合として行ったことが、適正価格での発注につながりました。 管理会社や設計コンサルタント主導で、業者選定をすると、見積り額が高くなりがちで、想定外の業者が安く提示してくると、安かろう悪かろうという理由で、選ばれないことが起こり勝ちとなります。 そういった事態を今回は回避できたということです。 業者選定の際は、単純に安いだけでなく、施工実績、技術力、アフターサービスなども総合的に評価することが重要で、知識のない管理組合が選択すると、品質面でのリスクも起こり得ます。 配管保全センターのように、中立的立場からアドバイスができる専門機関の支援があれば、そのようなリスクは避けられますが、中立的立場からアドバイスできるのは、どの機関かといった見極めも大切なポイントになります。3. 瑕疵(かし)保険の活用
三つ目の理由として、瑕疵保険を利用したということです。 従業員10名前後の施工会社の場合、その会社が万が一倒産したら、不具合があった時にどうするのかという心配があり、企業規模の大きい会社のほうが安心だという考え方もでてきます。 それに対して、ここ最近、国土交通省のホームページでも紹介されている下の5社が扱う瑕疵保険を活用することで、問題解決ができるようになりました。 この瑕疵保険に管理組合として加入すれば、万が一、施工業者が倒産しても工事完了後、10年間はこの瑕疵保険で不具合を直せるようになったのです。 これにより施工会社の規模にかかわらず安心して工事を依頼できるようになりました。 国交省のホームページに記載されている瑕疵保険を扱う業者: ①住宅あんしん保証 ②ハウスプラス住宅保証 ③ハウスジーメン ④住宅保証機構 ⑤日本住宅保証検査機構4. 見積もり時の価格変動への対応
四つ目の理由として、見積もり時に材料費の値上がりを許容する条件を設定したことです。 近年、資材価格や人件費の変動が激しく、見積もり時点と実際の工事時期で材料費や人件費が大きく変わることがあります。 一度出した見積もりは何カ月たっても何年たっても見直しはできないということであれば、見積もりを出す業者は値上がりを想定して、幅を持たせた見積もりを出さざるを得ません。 そこで、見積もりを出す前提として、総会上程時に再見積もりをしてもいいという条件で、業者が見積もりを出せるようにしました。 今回は想定していた総会の時期がそれほど先ではなかったので、再見積もりではなく、見積り額の1割程度を予備費とするということで済みました。このような経緯から、適切な業者選定をした結果、工事費用を大きく削減することができました。 これによって修繕積立金の節約になり、今後、浮いた資金で、他の修繕工事を行うこともできます。 大切なのは、理事会の皆さんが主体性を持って業者選定に取り組むことです。様々な選択肢を比較検討し、専門家のアドバイスも参考にしながら、最適な判断をすることが重要です。 配管保全センターでは、このような実例を元に、マンション管理組合の皆さんに役立つ情報を提供し続けています。 もし以上の内容で分からない点や、ご自身のマンションの配管について相談されたいことがございましたら、こちらからお気軽にお問い合わせください。
関連記事